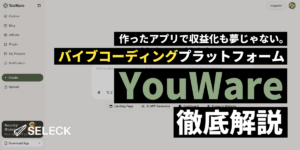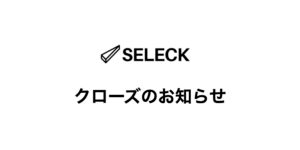- 株式会社リクルート
- サービスデザイン室 デザインマネジメントユニット
- 磯貝 直紀
プロダクト価値を最大化する「デザインディレクター」。リクルート・デザイン組織の進化

株式会社リクルートでは、2019年にデザイン職を横断的に束ねる組織「デザインマネジメントユニット」を正式に立ち上げた。
もともとは社内の有志による勉強会から始まったこの取り組みは、現在では90名を超える規模にまで拡大。ユニットに所属する全メンバーは「デザインディレクター」の肩書を持ち、領域横断で事業価値の最大化に取り組んでいる。
この職名には、デザインのケイパビリティをベースに、事業の本質や目的を理解した上で、プロダクトの価値を拡大していく役割を果たすという狙いがあるという。
その存在感が発揮されるシーンのひとつが、ゼロからイチを生み出す新規事業開発だ。初期段階からデザインディレクターが関与することによって、空中戦になりがちな議論を可視化し、理想像をプロトタイプとして提示するなど、より精度高くプロダクトを開発することができる。
今回は、デザインマネジメントユニットのユニット長を務める磯貝 直紀さんに、組織の立ち上げ背景から現在の運営体制、そして今後の展望までを伺った。
※聞き手:株式会社ゆめみ CDO 兼 プリンシパル・プロダクトデザイナー 野々山 正章さん
▼【左】リクルート磯貝さん、【右】ゆめみ野々山さん

「勉強会」から始まった横断組織が、現在は90名規模まで成長
野々山 本日はよろしくお願いします。まずは、磯貝さんがリクルートでデザイン組織を立ち上げた背景について聞かせてください。
磯貝 きっかけは、リクルートには「デザインを活用する余地がある」と感じたことです。
私が入社した2015年当時、社内にはまだ「デザイン職」という役割が存在していませんでした。実際にデザイナーが必要になった場合には、プロダクトマネージャーが外部の業務委託の方に依頼する、という状況だったんです。
だからこそ、社内にデザインにコミットする役割を定義できれば、より良いアウトプットが実現できるのではないかと考えました。
最初は、私のようにデザインのバックグラウンドを持つメンバー数名で集まって「デザインの重要性が理解されていないよね」とぼやくところからのスタートでした(笑)。そうしたネットワークが徐々に広がっていき、やがて事業を横断してナレッジを共有する「勉強会」的な動きへと発展していったんです。
 磯貝 とはいえ、そうした草の根活動を続けていてもインパクトは限定的だったため、 より大きな変化を起こすには、きちんと組織として立ち上げるべきだと考えました。 そこで役員に問題提起を行い、2019年に事業組織横断のデザイン組織を正式に設立しました。
磯貝 とはいえ、そうした草の根活動を続けていてもインパクトは限定的だったため、 より大きな変化を起こすには、きちんと組織として立ち上げるべきだと考えました。 そこで役員に問題提起を行い、2019年に事業組織横断のデザイン組織を正式に設立しました。
当初は10名にも満たない体制でしたが、現在では約90名にまで拡大。 事業を横断するデザイン組織として、各領域と連携しながら活動しています。
 野々山 そういった成長ストーリーがあったのですね。現状は「デザインマネジメントユニット」という名称ですが、リクルートの中ではどのような位置づけの組織ですか?
野々山 そういった成長ストーリーがあったのですね。現状は「デザインマネジメントユニット」という名称ですが、リクルートの中ではどのような位置づけの組織ですか?
磯貝 リクルートの中には、サービスデザイン室という、デジタルサービスの企画・構築・運用を担う約1,000名規模の組織があります。 その中で、デザイン職のみを集めた専門組織がデザインマネジメントユニットです。
プロダクトマネージャーやエンジニア、ビジネス職など他の職種とも密に連携しながら、 プロダクトの価値向上に取り組んでいます。
全員が「デザインディレクター」として「物事を動かす」組織
野々山 デザインマネジメントユニットは、現在どのような組織体制をとっていますか?
磯貝 リクルートには、『SUUMO』が担う住まい領域や、『ホットペッパービューティー』が担う美容領域など、事業ごとに領域が分かれています。デザインマネジメントユニットも同様に、各領域ごとに編成されており、それぞれの事業にも深く組み込まれたマトリクス型の構造になっています。
個別の事業にコミットしながら、領域横断型で情報流通やナレッジの底上げもできるという、いいとこ取りの体制を目指しています。
野々山 「デザイナー」とひと口に言っても、その職種やスキルセットは多岐にわたりますよね。ユニット内では、どのように役割を定義しているのでしょうか?
 磯貝 一般的には、スキルレベルや専門領域に応じて職種を細かく分けたり、評価項目を設定したりするケースが多いと思います。ただ、リクルートの場合は事業領域が非常に幅広く、それぞれのフェーズやビジネスモデルも多様です。
磯貝 一般的には、スキルレベルや専門領域に応じて職種を細かく分けたり、評価項目を設定したりするケースが多いと思います。ただ、リクルートの場合は事業領域が非常に幅広く、それぞれのフェーズやビジネスモデルも多様です。
そのため、個別に職種を定義していくと複雑になりすぎてしまう。そこで私たちは、すべてのデザイン職を「デザインディレクター」として一本化しています。
この職種の定義は、「デザインのケイパビリティをもって物事を動かし、プロダクトの価値を最大化する人」。それくらいの抽象度で捉えるようにしています。
大事なのは、会社の「物事の進め方」や「意思決定の流れ」を含めた文脈を、深く理解すること。ドメイン知識はもちろん、社内の決裁フローやステークホルダーの関係性も含めて把握したうえで、初めてデザインスキルが機能する、そんなイメージです。
我々は「動かすデザイン」というフィロソフィーを掲げていますが、単に手を動かしてデザインするだけではなく、物事を動かしていくための総合力が求められると考えています。実際の業務範囲としても、ユーザーやクライアントを幸せにするために、例えるなら自分たちができることならゴミ拾いでも何でもやる。価値創出につながるものであれば、何でもスコープになります。
実際に私自身のキャリアを振り返っても、これまで「何かやってくれる感じ」「何でもやってくれる感じ」で立ち回ってきたことで、重宝されていたんだろうなと思うんですよね。
野々山 いいですね。私も「何でもやるよ」という気持ちはいつも持っています。優れたデザイナーはデザインの対象が組織であれ、プロダクトであれ、会議体であれ、すべてがデザインだというマインドをもっていますよね。ただ、その姿は一般的にイメージされるデザイナーとは違うかもしれません。
磯貝 そうですね。一般的にイメージされる「デザイナー像」とは、かなり違うと思います。もともと私たちは、デザインという機能や手段だけを提供する「受託型の組織」にはしない、ということを大事にしてきたので。色や形を作ってくれる組織ではなくて、デザインを活用する組織ですよ、ということを最初から言っていました。
「デザイナー」という言葉には、どうしても特定の役割にとどまる印象やステレオタイプがつきまといます。だからこそ、あえて「デザインディレクター」という名称を用いていますし、役割や手段に固執することなく、事業にどう貢献できるかを最優先に考えて動いてほしいと伝えています。
最終的に重要なのは、スキルだけではなく「スタンス」なんですよね。 具体的には、視座の高さ、主体的に考え動く力、そして自分が何を求められているのかを正しく理解する力。私たちは、これらのスタンスを備えた人材を「デザイン拡張人材」と定義し、その育成に向けて、日々メンバー間で議論を重ねています。
野々山 スタンスを育てるためのアプローチやサポートとしては、具体的にどのようなことをされていますか?
磯貝 本人のやりたいことや価値観を1on1等を通じて深く本質的に吸い上げ、それを実現できるようなプロジェクトにできるだけアサインするようにしています。
やはり、自分がやりたい仕事であればモチベーション高く取り組めますし、結果にもつながりやすい。成果が出たらきちんと称賛して、さらに同じ方向性でより責任ある仕事を任せていく、そんなポジティブなスパイラルを回していくことが大切だと考えています。
こうしたマネジメントをマネージャー陣にも積極的に奨励していて、事例はチーム内で共有しています。まだ努力ベースの部分も多いですが、少しずつでも再現性を高めていけたらと思っています。
野々山 すると、アサインの変更や担当領域が変わることも多いのでしょうか?
磯貝 多いですね。事業フェーズとの相性も大きいです。「0→1」を生み出すフェーズが得意で好きな人もいれば、既存の仕組みを磨き上げていく「1→10」のフェーズが得意という人もいる。それぞれの志向や強みに合わせて、より力を発揮しやすい環境にアサインすることを意識しています。
ゼロイチの新規事業開発において、デザイナーが果たす役割は?
野々山 新規事業など、いわゆるゼロイチの開発においては、デザインディレクターはどのように関わっているのでしょうか?
磯貝 関わり方にはいくつかのパターンがありますが、まずひとつは完全な新規事業のケースです。リクルートには、新規事業開発を専門に担う組織があり、そこにデザインディレクターをアサインしてプロジェクトを進めていきます。
一方で、すでに事業領域として存在する「住まい」や「美容」などの中で新規事業や新機能を追加する場合は、もともとその領域を担当しているデザインディレクターの中から、不確実性に強いメンバーが担当をするケースが多いです。
 野々山 新規事業開発のプロセスでは、デザインディレクターはどのような役割を担っているのでしょうか?
野々山 新規事業開発のプロセスでは、デザインディレクターはどのような役割を担っているのでしょうか?
磯貝 なるべく早い段階、つまり「この事業で何を実現したいのか」といった抽象度の高い議論のフェーズから関わるようにしています。その中で、デザインディレクターはファシリテーターのような立ち位置をとり、議論を可視化していきます。
例えば、「この事業で実現したい理想像はこういうことですよね」という仮説を、プロトタイプという形で提示する。それをもとに関係者の目線を揃えたり、検証を進めたりしながら、議論を具体的に前進させていく。そんな関わり方が多いですね。
野々山 ファシリテーションやプロトタイピングなど、不確実性の高いことを前に進めていく職能は今の時代のデザイナーに必要ですよね。ただ、すぐに実践できる人材は限られている印象です。
磯貝 おっしゃる通りで、こうすれば正解、という特定の「型」のようなものは存在しないと思います。企業やドメインごとの文脈や進め方を深く理解したうえで、デザインスキルをどう組み合わせていくかが求められますね。
デザインマネジメントユニットでは、そうした役割まで含めて我々が担うんだ、というメッセージングをしています。また、実際にデザインディレクターがプロダクト開発を前に進めた事例などを組織内でも共有していますね。
例えば、 「リクルートダイレクトスカウト」のリニューアル事例では、初期段階からデザインディレクターが参画し、求職者や企業にとっての理想の体験を定義するところから始まりました。
具体的には、プロトタイプを作成し、他職種とともにプロダクトのビジョニングを実施。そこからリリースまで一貫して理想像に近づけるプロセスを進めることができました。
 野々山 今の事例もそうですが、ゼロイチのフェーズにおいてデザインディレクターが関与することに対して、社内からはどのような反応がありますか?
野々山 今の事例もそうですが、ゼロイチのフェーズにおいてデザインディレクターが関与することに対して、社内からはどのような反応がありますか?
磯貝 実は、完全なゼロイチの新規事業にも私たちが本格的に関わるようになったのは昨年度からなんです。現在も進行中のあるプロジェクトでは、事業責任者から「もっと早く関わってもらえばよかった」と言ってもらえるほどで、私たちが初期から関与することの価値をあらためて実感しています。
デザインを機能や手段として語らず、目的や本質をとらえる
野々山 お話を聞いていると、リクルートはデザインと相性がいい組織なのではという印象をもちました。
磯貝 そうですね。リクルートでは、いわゆる「広義のデザイン」に対する意識が全職種に浸透していると感じます。また、職種間の「越境」をポジティブに捉える文化があるので、デザインのスキルをベースにしながら他の領域にオーバーラップして働くスタイルが受け入れられやすい組織ではあります。
ただ、私が入社した当初は、まさにグロースハック全盛期で、社内はかなり「定量ドリブン」な文化でした。 数値で測れないものには価値が置かれにくく、デザインのように間接的にプロダクトへ貢献する領域には、なかなか投資がされづらかったんです。
そうした状況のなかで、「デザイン組織は役に立つんだ」という信頼を少しずつ積み上げてきました。そして、ようやく最近になって、面白いチャレンジに関わらせてもらえる機会が増えてきた実感があります。
野々山 デザイン職が信頼を勝ち得ていくためには、何が必要だと思いますか?
 磯貝 大切なのは、目的や本質をとらえた上で、ゴールに近づくために主体的に動けることだと思います。
磯貝 大切なのは、目的や本質をとらえた上で、ゴールに近づくために主体的に動けることだと思います。
プロジェクトに関わる人が、必ずしも正確で本質的な指示をくれるとは限りませんよね。そんなときに、表面的な依頼をそのまま受け取るのではなく、「こうしたほうが本質的に良くなるのでは?」と逆提案できる力が、信頼につながっていくと感じています。
そして、デザインを機能や手段として語らないことも重要です。例えば、デザイナーが状況を加味せず安易に「デザインをリニューアルしてみましょう」と提案するケースがありますが、提案された側からすると「今の事業の状況を考えて、本当に必要なの?」と思ってしまうような内容ではがっかりされてしまいます。
だから、組織や事業の状態や目的をしっかりと見据えて、自分のケイパビリティで何ができるかをしっかりと考えて行動することが大事です。
野々山 「営業やプロダクトマネージャーに権力が集中していて、デザイナーの進言があまり聞き入れてもらえない」という悩みを聞くことが多くあります。リクルートの、事業側とデザイン職が事業視点で語り合えるカルチャーは元々あったものなのでしょうか?それとも作り上げていったのですか?
磯貝 風土がもともとフラットですね。提案が目的につながっていることを論理的に話せば、プレイヤーや職種に関係なく話が通じやすいと思います。ただ、おっしゃるケースも理解できますし、リクルートでも話しても伝わらない場面はあります。
そんなときは、どんな方法でもいいから合意形成できればいいと私は考えています。極論、一緒に飲みに行ったりして仲良くなることもひとつのソリューションです。引き出しを増やすことが大事ですよね。
デザインの役割も進化し続ける。「型」ではなく「適応」する組織へ
野々山 最後に、デザインマネジメントユニットの今後のチャレンジについて教えてください。
磯貝 私たちは、既存事業、新規事業問わず、新規性のある不確実性の高い事業案件において、デザインがより力を発揮できるような体制を広げていきたいと考えています。徐々に成果が出始めているので、これからはその再現性を高め、さらに価値創出のスケールを大きくしていく。それが当面のチャレンジです。
また、デザイナーの役割そのものも今後ますます変化していくはずです。私たちは固定的な職能ではなく、柔軟なフレームで役割を定義しているため、環境変化にも適応できる強みがあります。これからも、時流を読みながら、常に進化し続けるデザイン組織でありたいと思っています。
野々山 AIなどの技術進化により、単にデザインを「つくる」だけでは差別化が難しい時代になっています。そうした中で、受託型でなく自ら価値を創出することを重視してきたリクルートの取り組みは、これからの時代にますます必要とされると感じました。本日はありがとうございました。(了)
ライター:久保 佳那
企画・取材・編集:舟迫 鈴(SELECK編集部)