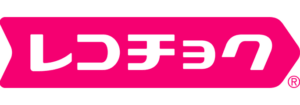
- 株式会社レコチョク
- 執行役員
- 松嶋 陽太
社内利用率90%を実現。レコチョクの「with AI プロジェクト」が生み出した業務革新

ChatGPTの登場から約2年。生成AIの急速な普及により、多くの企業がAI活用の検討を始めている。しかし、業界特有の規制や慣習、経営層の理解不足、社員のリテラシー格差など、AI導入には様々な壁が立ちはだかる。
それゆえ、実際に全社規模での導入を成功させ、日常業務に根付かせている企業はそれほど多くない。
そんな中、音楽業界でいち早くAI技術を全社展開し、「社内のAI利用率90%」という数字を達成したのが株式会社レコチョクだ。
同社は2001年の創業以来、「着うた」の実装からチケット型NFTの発行・販売まで、常に音楽業界の技術革新を牽引してきた。2023年6月に立ち上げた「with AI プロジェクト」では、単なるツール導入にとどまらず、AIを前提とした組織変革と業務プロセスの再設計に取り組んでいる。
今回は、同社の執行役員を務める松嶋 陽太さんに、社内の業務効率化から音楽業界全体への価値提供まで、AIを軸とした戦略をどう描いているのか、詳しく話を伺った。
テクノロジーと音楽の融合を20年以上牽引してきた、レコチョクのDNA
私は、Windows95が登場した頃に、キヤノンコピア販売株式会社(現:キヤノンシステムアンドサポート株式会社)に就職しました。その後、フリーランスとしてベンチャー企業の立ち上げに2社ほど携わり、2009年にレクチョクに入社しました。
当時は開発体制の内製化に舵を切るタイミングだったため、私はその推進役を担いながら、時代の変化に合わせて先進技術の検証・実装を手がけてきました。
例えば、AWSの登場時にはシステム全体のクラウド移行を実現したり、Web3の音楽業界での活用可能性を検討してきました。現在は、急速に進化するAI技術が、音楽業界や当社の事業全体にどういったインパクトを与えるのかを見極めながら業務に取り組んでいます。
 レコチョクは、2001年に国内主要レコード会社の共同出資により誕生した企業です。現在は「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、音楽配信事業、権利者向けのデジタルソリューション事業などを展開しています。
レコチョクは、2001年に国内主要レコード会社の共同出資により誕生した企業です。現在は「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、音楽配信事業、権利者向けのデジタルソリューション事業などを展開しています。
多くの方がレコチョクに対して、「レガシーな企業」というイメージをもたれているかもしれません。しかし実際は、音楽に付加価値を生み出すため、常にテクノロジーの進化にアンテナを張り、先手を打って新しい価値を音楽業界に届けてきた企業です。
例えば、2002年には「着うた」をいち早く配信開始。さらにスマートフォンの普及時には、早期にサブスクリプション型の音楽配信サービスに参入したり、2021年にはNFTを活用したチケット販売を開始するなど、テクノロジーと音楽の融合を常に具現化してきました。
こうした姿勢の積み重ねが、AIやWeb3といった新技術に対しても積極的に取り組み、柔軟に受け入れる企業風土の土台となっていると感じています。
▼レコチョクの歴史を振り返るコンセプトムービー(2025年4月公開)
全社員がAIを使いこなす組織へ。「with AI プロジェクト」とは?
長年インターネット業界に携わってきた私にとって、2022年のChatGPT登場は大きな衝撃でした。「これは、間違いなく大きな変化を起こす」と直感的に感じましたね。
時間とともにその精度が改善されることは明らかでしたし、AI活用の実績が生まれてきてからでは時流に乗り遅れてしまう。そう思い、早期の段階から社内のメンバーでAIに触れ、より理解を深めることが何よりも重要だと考えました。
さらに、開発の内製化という文脈では、社員自身がAIを使いこなすことが不可欠だと考えていました。外部の委託先に依存し、業務委託のメンバーがAIを使う形になってしまっては、ロジックが不透明になってしまいますからね。
こうした背景から、2023年6月にスタートさせたのが「with AI プロジェクト」です。AIと共に社内の業務生産性を向上させること、そして、蓄積した知識やノウハウをもとに音楽業界にソリューションビジネスを展開することをゴールに定めています。
使用ツールとしては、まず、業務生産性の向上が大幅に見込まれるエンジニア領域に向けて、ChatGPT Plus、Azure OpenAI Service、Github Copilotの社内導入を推進。さらに立ち上げから2ヶ月後には、全社員が業務でChatGPTを活用できるように「RecoChat with AI(以下、RecoChat)」を構築しました。
現在、ビジネスサイドではPDFで保管されていたアーティストのメタデータのデジタル化、海外向けローカライズ、見積書や請求書の内容確認などでAIを活用。開発チームではコーディング支援やテストコードの作成、技術的な疑問解決にAIが利用されています。
▼現在の「RecoChat with AI」利用画面(※UIは今後、リニューアルを計画中)
 with AI プロジェクトは、セキュリティ責任者、社内IT部門責任者、エンジニアリングマネージャーなどの5名で立ち上げました。少数精鋭にすることで迅速な意思決定を実現し、加えて、各部門の責任者を配置することで部署メンバーの目標設定に反映させ、AI導入を組織全体で加速させるねらいもありました。
with AI プロジェクトは、セキュリティ責任者、社内IT部門責任者、エンジニアリングマネージャーなどの5名で立ち上げました。少数精鋭にすることで迅速な意思決定を実現し、加えて、各部門の責任者を配置することで部署メンバーの目標設定に反映させ、AI導入を組織全体で加速させるねらいもありました。
ただ、当初はChatGPTが業務で本格的に活用できるレベルには至っておらず、「さすがに業務にはまだ使えない」といった否定的な声が多かったのも事実です。
一方で、AIに関しては社会全体で注目が高まり、著名経営者らが「AIは必須」と発信していたことで説得力が増し、導入の後押しとなりました。
加えて、開発人員における業務委託の削減といった具体的なKPIを立て、AIの導入が経営に与えるインパクトを数値的に示すことで、スムーズにプロジェクトを推進できたと思いますね。
「社内のAI利用率90%」を達成した、AI推進における3つの取り組み
現在、RecoChatは月間で社員の9割以上が利用するツールへと成長しています。活用を推進するにあたって取り組んだことは大きく3つです。
1つ目は、経営層を含む全社員向けに外部講師による講演を実施したことです。「AIの進化や事業への影響」をテーマに、AIに対する危機感や必要性をしっかり共有する機会を設け、全社で共通認識を作ることから着手しました。
2つ目は、日常業務の中で社員がAIを使う具体的な場面を設けたことです。たとえば、当社では社員の評価制度と連動するMBO(目標管理制度)を半期に一度作成しますが、目標の書き方にばらつきが出やすく、上司とのやりとりが何度も繰り返されるという課題がありました。
そこで、目標を設定する前にAIとやり取りをして精度を高めるためのプロンプトを社員に提供し、日常的にAIと触れる機会を創出しました。
3つ目は社内ノウハウの共有です。導入初期は「AIをどう使えばいいのか」が曖昧だったため、社内勉強会を開いて学びを深める仕組みを取り入れました。
また、社員がいつでも質問できる「AI相談窓口」をTeams上に用意したり、月に一度、オフィスアワー形式で社員が気軽に質問できる時間も設けています。
▼社内勉強会の様子
 仕組みの構築にあたって工夫した点は、プロダクトファーストの思想で設計し、柔軟性のあるプラットフォームにしたことです。RecoChatにさまざまなプラグインを用意し、それぞれに専用プロンプトを設定しています。
仕組みの構築にあたって工夫した点は、プロダクトファーストの思想で設計し、柔軟性のあるプラットフォームにしたことです。RecoChatにさまざまなプラグインを用意し、それぞれに専用プロンプトを設定しています。
例えば、QA(品質保証)チームのメンバーが事象報告、いわゆる障害報告を作成するためのプロンプトや、レコチョクの情報をまだ十分に把握していない新入社員が必要な情報を取得できるプラグインなどです。
また、あらゆるSaaSを接続可能にし、GitHubなど外部サービスの情報も簡単に取り込めるようにしています。現在は、社内の情報基盤を共通化する動きの一環としてMCP(Model Context Protocol)のような仕組みを整備し、AIが社内データにリアルタイムでアクセスできる環境の整備を進めているところです。
※プラグイン作成の詳細については、こちらの記事もぜひ一緒にご覧ください:RecoChat with AI上でプラグイン完成までの奮闘記(レコチョクのエンジニアブログ)
企画者と開発者の境界を溶かす。目指すは、開発プロセス全体のAI化
「with AI プロジェクト」は2025年で3年目を迎え、これまでの成果を踏まえて次のステップへと進んでいます。
プログラミング開発など個別業務の効率化は実現できましたが、会社全体への貢献度を定量的に示せていないのが現在の課題です。そこで「あらゆる業務でAIを活用することを目指し、より大胆な改革を進める」ことを新たな目標に掲げ、業務効率化から売上貢献へとフォーカスをシフトさせています。
開発チームでは、要件定義からUXデザイン、開発、テストに至る開発プロセス全体でAIを活用することを最終目標に据えています。特に注力したいのが要件定義のフェーズです。これまでは非エンジニアのメンバーが要件定義を作成していたため、エンジニアとの間で多くのやり取りが発生していたんです。
しかし、そのやり取りはある程度パターン化できるため、エンジニアが求める観点をプロンプトとしてあらかじめ用意し、AIで要件定義書の精度を高めてからエンジニアと連携することで、このやり取りを大幅に削減しようと試みています。
 今後は、AIによって「開発者」と「企画者」の境界がますます曖昧になっていくと思っていて。
今後は、AIによって「開発者」と「企画者」の境界がますます曖昧になっていくと思っていて。
企画者が要件をまとめてエンジニアに渡し、そこからUI/UXの設計・実装に進む流れが主流でしたが、今では企画者自身がAIの力を借りてプロトタイプを簡単に作れるようになりました。
こうした変化に対応していくためにも、AIを前提とした新しい役割や開発プロセスの設計が重要になると思いますし、現場では、プロトタイピングのスキルが企画・開発者のどちらの立場にも求められるようになるでしょう。
音楽業界への展開と社内変革。AI活用で描く、これからの成長戦略
これまでの取り組みを通じて、音楽業界の業務効率化を目的としたAI活用の受託開発にすでに着手しており、すでに一定の成果が出ています。
社内でも、先日実施したアンケートでは「何の業務でどのように使っているのか」の具体例が多数挙がり、日々の業務の中で自然にAIが活用される状態に近づいてきていると感じます。
今後の展望としては、まず音楽業界へのアプローチを加速させていきたいです。音楽業界の現状は、一部の社員がAIツールを業務で使用している段階で、楽曲制作では技術的にも著作権の観点や運用的にも課題が多く、AIを積極的に活用するレベルには至っていません。
そのため、受託開発という形で業界に深く入り込みながら、この3年間でしっかりと売上を立てていくことを1つの柱に据えています。
もう1つは、社内業務を最大限に効率化し、売上につなげていくことです。そのために必要なのが、社員のスキルや意識の底上げです。
AIはあくまでアドバイスをくれる支援ツールであり、最終的な判断や意思決定は人間が行うべきものです。しかし、この前提を外してしまうとAIの回答に依存し、それがリスクにもなり得るため、正しく使いこなすためのリテラシー醸成が不可欠です。
そして、社員によって、AIのリテラシーや活用方法にばらつきがあるからこそ、AIスキルの可視化と育成が重要です。「基本的な利用ができる」「AIの特性やクセを理解している」「業務や事業に応用できている」など、社員のスキルを5段階で評価するような仕組みを設計し、社員が着実にスキルアップできるような教育体制をHRサービスグループと連携しながら整えているところです。
このようにAI活用の環境を徐々に整えていきながら、社員一人ひとりの職能を拡張していく方向にシフトし、挑戦と成長を支援する仕組みを引き続き整えていきたいですね。(了)
企画・取材・ライター:古田島 大介
編集:吉井 萌里(SELECK編集部)
【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド
近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。
情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。
そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。








