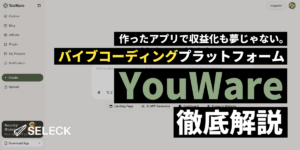- 株式会社ABEJA
- ABEJA Insight for Retail / Product Owner
- 齋藤 和正
「真にデータドリブンな組織」を目指して。全員が同じ指標を追う、最速チームの作り方

〜ユーザーのニーズをすばやくプロダクトに反映するため、ビジネスチームと開発チームの「情報格差」を排除。チームの垣根をなくす、データドリブンな組織づくり〜
近年、あらゆる業界で、収集したデータを分析して意思決定に役立てる「データドリブン」思考の重要性が高まっている。
2012年9月の創業以来、AIの社会実装を手掛けてきた、株式会社ABEJA。「イノベーションで世界を変える」というビジョンを掲げ、米Google本社から日本で初めて出資を受けたベンチャー企業としても、注目を集めている。
同社が展開する、小売・流通業界向けの店舗解析SaaS「ABEJA Insight for Retail」のチームでは、顧客に対して「データを活用して店舗運営を改善しましょう」と提言していた一方で、自組織がデータを活用しきれていないという課題感があったという。
そこで、「ビジネスチームと開発チームの横断プロジェクト体制の構築」「ビジネスメンバー向けのデータ分析勉強会」などの施策を実行し、データドリブンな組織への変革を推進。
ビジネスチームと開発チームの共通言語が増えたことで、同じデータを元に判断できるようになり、意思決定スピードが向上。さらに、以前は開発チームまで届いていなかったクライアントの声を、プロダクト開発にも還元できるようになったそうだ。
今回は、同サービスのプロダクトオーナー 兼 開発チームリーダーを務める齋藤 和正さんに、データドリブンな組織づくりについて、詳しくお伺いした。
ロードマップがない中、「データドリブンな組織づくり」をビジョンに
私は、2018年4月に、データサイエンティストとしてABEJAに新卒入社しました。同年12月から、AIを活用した店舗解析SaaS「ABEJA Insight for Retail」のプロダクトオーナー(以下、PO) 兼 開発チームリーダーとして、プロダクトの設計や開発チームのリードなどを担っています。
ABEJA Insight for Retailは、店舗に設置したカメラやセンサーなどのIoTデバイスから取得したデータを分析して、あらゆる顧客行動データを見える化し、店舗運営の改善施策に関する効果検証を可能にするサービスです。
私がPOになった頃、機械学習のモデル開発やIoTデバイスの管理といった弊社の技術力を、十分にプロダクトの価値につなげられていないことが課題でした。
当時は、大規模な部署異動があった直後で、開発チームに残ったメンバーは4人ほど。リソースが圧倒的に足りておらず、開発スピードが落ちてしまっていました。
ビジネスメンバーからは「開発チームに言ってもなかなか対応してもらえない…」といった諦めの声も上がっている状況でしたね。
また、カスタマーサクセスと開発チームとの連携不足によって、お客様の声が開発チームまで届かず、「本当に今のサービスのままで良いのか」を検証することもできていませんでした。
そして何より問題だったのが、明確なプロダクトのロードマップがないことでした。

そこで最初に、新体制におけるプロダクトのビジョンを描き、そこにメンバーを巻き込んでいくことから始めました。
また、本当の意味でお客様にとって価値のあるプロダクトを届けていくためには、チームのビジョンも必要です。そこで掲げたのが、「私たち自身が真にデータドリブンな組織になる」でした。
というのも、お客様に対して「データを活用して店舗運営を改善しましょう」と伝えていたにも関わらず、私たち自身、十分にはデータを活用できていなかった。
お客様に訴求している価値を、まずは自分たちが体現できるようになるために、データドリブンな組織づくりをスタートしました。
情報格差を無くすことが、価値創出のスピードアップにつながる
チームビジョンの実現にあたって、具体的に取り組みたいことが3つありました。
ひとつは、データを使ったプロダクトのプロトタイプの構築。次に、レポート提供などを通じた顧客に対するデータの還元。そして最後が、全メンバー共通のKPI管理とプロダクト改善のためのユーザー行動の分析でした。
これらを実現するためには、ビジネスチームと開発チームが同じビジョンに向かい、情報格差をなくすことが大事だと思っていて。それこそが、価値創出のスピードアップにつながると信じていたんです。
なので、まずはチームの垣根なく、お客様に向き合うことができる関係性と体制づくりに取り組みました。
私がPOになってから、四半期ごとの計画をプロジェクトベースで推進する形にしたのですが、意識的にビジネスチームと開発チームの「横断型」の体制にしました。
例えば、お客様用のダッシュボード開発プロジェクトや、サポート体制の改善プロジェクトでは、ビジネスメンバーとエンジニアが同じプロジェクトメンバーとして協働することで、お客様のニーズをすばやく開発に反映できるようにしました。
そして、プロジェクトの進捗管理には、ビジネスチームのメンバー含めて全員でGitHubを使いました。
とにかくプロジェクト制で進めることを強調したかったので、プロジェクトごとにかっこいいロゴやアイコンを作ったりもしましたね(笑)。

当時は、私が全てのプロジェクトのミーティングに入ってハブになることで、プロジェクトの独立性を保ちながら情報連携できるように工夫していました。
四半期ごとに10〜20個以上のプロジェクトが走るので結構大変でしたが、最初はめちゃくちゃ丁寧に認識合わせをすることを大事にしていましたね。
3段階に分けて、チームを変える。実践してこそ「技術」が身につく
こうして横断型のプロジェクトベースを導入し、チームの垣根なく働ける環境を整えた上で、いよいよデータドリブンな組織に変革するための施策をスタートしました。
まずはじめに、メンバー全員がデータ分析できる環境を構築するため、BIツールのひとつ「Redash」を使い、社内のあらゆるデータをSQLで取得できるようにしました。
これによって、顧客のマスター情報や、実際にプロダクトで提供している集計データなどに、チームメンバー全員がアクセスできるようになりました。
次に、「データ分析スキルの向上」を目的として、SQLの書き方や機械学習サービスの使い方などをテーマに、ビジネスメンバー向けの勉強会を実施しました。
この勉強会は、週1回、7週かけて行いました。参加した10〜15人のビジネスメンバーに、エンジニアなどの担当者が持ち回りで教える形です。
データ分析の基本を学ぶことに加えて、ビジネスと開発の垣根をこえて「チームの一体感」を感じられるようにすることも狙いでした。そこで、簡単な認定制度を設けて、チームのデータ活用促進の貢献度に応じた金・銀の認定バッジも用意しました。
▼認定バッジを胸にしたエンジニアメンバー(※同社提供)

こうしてデータに対する心理的ハードルを下げたあとは、いよいよ「プロジェクト業務内でのデータ活用の実践」です。勉強して終わりにならないように、それを実践する場として、SQLを使う機会があるプロジェクトを設けました。
お客様に対する価値提供のスピードを上げるには、「データサイエンティストだけが分析できる」という状態はボトルネックになりかねません。
そこで、ここではデータサイエンティストはあえて自分の手を動かさずに、ビジネスメンバーのサポートに回ることを意識しました。
結果として、自主的に勉強を継続するビジネスメンバーや、中には「エンジニアよりもSQLが書ける」メンバーも現れ、エンジニアが焦ることもありましたね(笑)。
ですが、やっている中で躓くことももちろんあります。それに対しては、Slack上に「SQLビギナー向けの質問チャンネル」を作成したり、一緒にSQLを見たり書いたりできる「もくもく会」を毎週実施したりすることで、サポートしています。
同じ指標を追い、チーム一体となってプロダクトの価値を高める
こうした取り組みを経て、今は開発チーム、ビジネスチームを問わず、チーム全員が同じ指標を追って、データを活用しながら改善施策を実施することができています。
私たちのサービスはSaaSのビジネスモデルなので、最重要指標はMRR(月次経常収益)に置いていますが、これとは別に、細かいKPIリストを作成しています。
その中で最も重要な指標を、カスタマーサクセスと開発メンバーを中心に議論して、四半期ごとに定め、改善を進めている形です。
例えば、トライアル導入中のお客様に本格導入に移行していただくためには、毎週のユーザーアクティブ率が重要なKPIになります。
あるお客様のアクティブ率を改善するプロジェクトのときには、ビジネスメンバーと開発メンバーが協力してユーザーのデータ分析を行ったり、お客様へのプロトタイプの提供を行ったりすることで、大幅にKPIを改善することができました。
このように共通の指標を追うことで、チームが一体となって課題解決に取り組むことができるようになったと思います。
また、ビジネスメンバーにも基礎的なデータ活用スキルが身についたことで、一次障害の対応や顧客データの数値異常の検知など、これまではエンジニアに依頼していたようなことでも、各自で解決できることが増えました。
さらに、システムにどんなデータがあるかという理解が深まったことで、「新しくこんなこともできるんじゃないか」と、ビジネスメンバーが主体的に考えられるようになったことも大きいですね。

データを踏まえて、自分たちが意志を持って前に進むことが重要
私は、お客様に価値あるプロダクトを届けるために、「チーム全員でひとつの指標を追いかけ、楽しく働く」という状態を実現したかった。そのための一つの手段がデータドリブンな組織づくりでした。
私たちのプロダクトの性質上、何をするにもデータがついてきます。なので、データを活用することは「当たり前」。ただ、データが全てだとは思っていません。
お客様と距離が近いサクセスチームの意見を積極的に取り入れることはもちろん、開発メンバーも実際にお客様のところに行き、よくヒアリングをしています。データだけでは見えないことも踏まえて、意思決定をすることが大事だと思っていますね。
これまで1年ほどかけて新しい体制を整えて、顧客に価値のある機能を継続的に提供できる状態まで持ってくることができました。
今後も、みんながプロジェクトの中で当たり前にデータを活用して、主体的に意思決定していけるような組織にしていきたいと思います。(了)