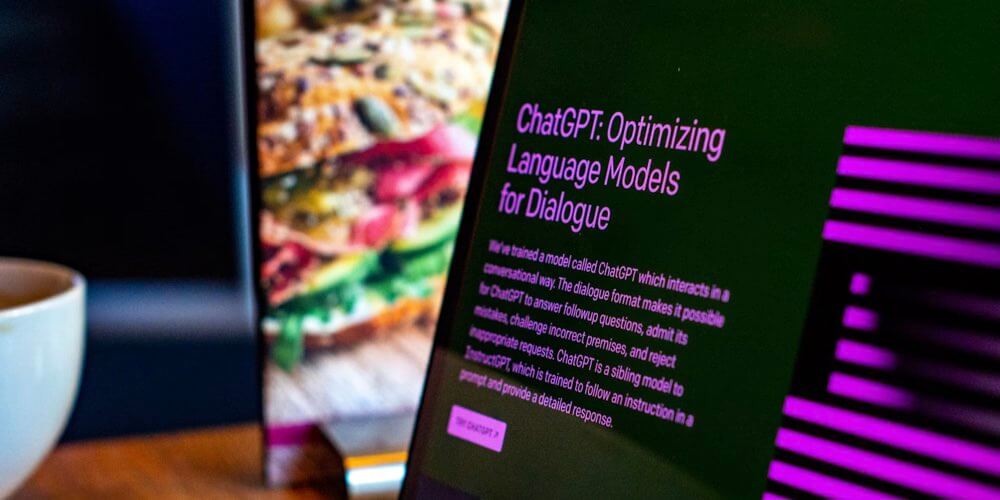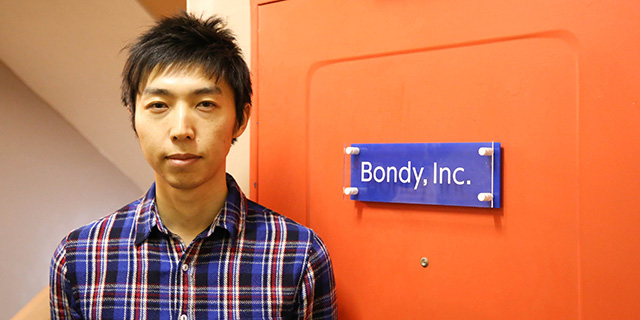- 株式会社WHOM
- 代表取締役 CEO
- 早瀬 恭
海外の最新HRtechも!スタートアップ採用トレンド大解説【SELECK miniLIVEレポート】

「SELECK miniLIVE」は、注目企業からゲストスピーカーをお招きし、X(旧Twitter)スペース上で30分間の音声配信を行う連載企画です。
2024年5月28日に開催した本回に登壇いただいたのは、株式会社WHOM 代表取締役 CEOの早瀬 恭さん(@Kyoporation)。本企画の新シリーズ「スタートアップの採用術」第1回のゲストスピーカーとしてお呼びしました。
シリーズ「スタートアップの採用術」
ますます激戦を極める、スタートアップ界隈における「人材採用」。
本シリーズでは、各社の採用施策における工夫や知見をカジュアルに公開していくことで、相互に学び合い、採用する側・される側、相互の体験向上に寄与することを狙いとしています。
早瀬さんは、インド、シンガポール、インドネシアでの人材紹介業界の経験を経て、2019年にはリンクトイン・ジャパンにジョイン。事業部長を経験後、2020年に「採用を強化したい企業とプロのリクルーターを繋ぐ」WHOMを創業しました。
今回は、国内外の採用領域について多彩な知識と経験をお持ちの早瀬さんに、海外スタートアップが取り入れている最新のHRtechや、日本の採用市場の今後の展望について、詳しくお話を聞きました。
(聞き手:株式会社ゆめみ / Webメディア「SELECK」編集長 舟迫 鈴)
本記事は、2024年5月28日に開催したSELECK miniLIVEの生配信を書き起こしした上で、読みやすさ・わかりやすさを優先し編集したものです。当日の音声アーカイブはこちらからお聞きいただけます。
日本の採用は「脱・エージェント依存」に向けた過渡期にある
舟迫 最初に早瀬さんの自己紹介をお願いできればと思います。
早瀬 WHOMの代表をしている早瀬と申します。キャリアはもともと、JACリクルートメントという人材紹介会社の出身ですが、ほとんどの期間を海外で過ごしました。インド法人の立ち上げから、シンガポール、インドネシアを経て日本に戻ってきました。その後、リンクトイン・ジャパンで事業部長を務めた後、WHOMを創業しています。
日本の採用事情にはもちろん詳しいですが、アジアを中心とした海外、そしてシリコンバレーの最先端の採用にも詳しいことが、人とは違う点かなと思っています。
舟迫 2020年にWHOMを創業された際は、それまでの海外でのご経験を踏まえて日本の採用に殴り込み、みたいなお気持ちだったんですか?(笑)
早瀬 そうですね(笑)日本の採用は、今ちょうど過渡期にあると思っていて。
いきなり海外との違いの話になりますが、シンガポールやアメリカといった先進国では、エージェント経由での採用はマイノリティなんですね。いわゆる紹介手数料も20%前後で、日本と比較するとだいぶ安い。
舟迫 日本ですと、エージェントさんのフィーは3割くらいですか?
早瀬 35%が相場でしたが、最近は40%が散見されるようになってきています。それは、採用自体が激戦ということでもありますが、やはり採用担当者の怠慢でもあると思っていて。
自分たちで採用をする、ということに十分にリソースを充てずにエージェントに頼ってきてしまった歴史があるんですよね。今まさにそこから変革しようとしているのが、日本の現状だと私は見ています。
▼株式会社WHOM 代表取締役 CEOの早瀬 恭さん

「転職活動は秘密裏に」「そもそも応募しない」のが日本人?
舟迫 海外では、どういった採用手法がメジャーですか?
早瀬 基本的にはダイレクトリクルーティング、つまり採用側から声をかける手法です。加えて、いわゆる媒体に出して応募を待つなど、インバウンド、アウトバウンド両方の採用手法がとられています。
ただ、基本的に海外は「応募文化」で、迷ったら応募しちゃう求職者が多いので、そこが日本と一番違うところです。日本の人って、本当に応募しない。「絶対に転職するぞ」くらいの温度感まで高まらないと応募しないので、手法というより、マインドの違いがポイントかな。
最近は変わってきたので良い傾向だと思いますが、日本にはいわゆる「転職を美徳としない」文化もまだ残っているので。結果的に候補者側も「秘密裏に転職活動をしたい」ということで、エージェントに頼ってきてしまった現状があります。
舟迫 すごくわかります。
早瀬 それに加えて、海外の場合は各国にひとつずつ「圧倒的に強い媒体」があるんです。
例えばアメリカではLinkedInを見れば、候補者の7割くらいは出てくる印象です。一方で、日本は色々なところに候補者が分散してしまっているので、採用担当者は本当に大変です。
舟迫 なるほど。とはいえ日本でも、特にスタートアップ界隈はカジュアル面談だったり、自分から気軽に応募する人も増えてきていますよね。
早瀬 そうですね。まさにそれが先ほどお伝えした「過渡期にある」ということです。日本でも「どんどん転職すれば良い」という文化も出てきていますし、カジュアル面談を行う企業も増え、転職のハードルが三段くらい下がってきた印象があります。それはすごく良いことなんじゃないかな、というふうに見ています。
ショート動画、AI活用など、新しいHRtechがトレンドに
舟迫 日本のスタートアップが真似できそうな、海外の採用手法はありますか?
早瀬 採用の手法自体に魔法はないので、そんなに「真似できる」ポイントはないかなと思います。ただ、新しいテクノロジーを活用した採用活動については、やはり海外の方が進んでいる印象です。
具体的にはふたつありますが、まずひとつめは、いわゆるChatGPTなどを活用して、採用のコンテンツを作っていくこと。求人票の作成、スカウトメールのカスタマイズといった文字を使う場面で、ChatGPTの知識を参考にすることはもう一般的になっています。
もうひとつは、いわゆるメールマーケティングの手法なのですが…。例えば、カリフォルニアのサンタモニカに住んでいる人に、サンタモニカにある会社から急にスカウトのメールが届く。
そのメールを開くと、あたかもその人に向けて作られたような動画で、企業の説明や、社長からのメッセージが流れる。そしてカジュアル面談に進むことを促される、みたいな採用手法が流行り始めているんですよね。
舟迫 それは要するに、1to1でカスタマイズされたメールを企業が候補者の方に直接送っている、ということですか?
早瀬 いえ、1to1に「見せられる」だけですね。そういったHRtechのサービスがアメリカで多く出てきているんです。
舟迫 企業がどこからかその人のメールアドレスを入手していると…
早瀬 シンガポールにいるときも、LinkedInに登録された人のメールアドレスを抜き出せるブラウザのプラグインがあったりしたので、そういった個人情報の部分は日本ほど目くじらを立てる人はいない印象です。
背景としては、結局スカウトサイトでメッセージを送っても、サイトにログインする一手間があるので、最近は開封率が落ちてきているんですよね。
舟迫 メッセージも実は全部コピペだったり、代表ではない人が「代表です」と送ったり、ユーザーも気がついていますよね。
早瀬 もうバレてますよね(笑)そういう意味で、より1to1っぽいものが必要とされていると。
それと、これはまだ私もそこまで詳しくないのですが、ショート動画も流行っていますね。企業がショート動画をSNS上にアップするのももちろんですが、採用を検討している方たち向けに、それぞれカスタマイズされたショート動画を送るといった、いわゆる行動喚起の材料としての位置づけもあるようです。
舟迫 それこそAIを使って、1to1のように見せられるショート動画を大量に作るとか?
早瀬 もうほぼほぼ、そういう世界になってきています。そうでなくても、ショート動画の作成自体にあまり工数はかかりませんし。
私は今年40歳になるのですが、これはなかなか世代を越えて考えを深めなければいけない部分だと思っています。ショート動画ってちょっと恥ずかしいですが、そこまでしなければ若い世代には刺さらない。やらないよりやった方がいいですよね、絶対。
舟迫 こうしてお話を聞いていると、日本はやはりテクノロジー活用では遅れていますよね…。
早瀬 日本の採用はだいぶガラパゴス化してしまったので…遅れているというか、変だと思います(笑)
採用を「人事の登竜門」と捉えず、長いスパンで向き合うべき
舟迫 日本の採用担当者の方に向けたアドバイスはありますか?
早瀬 ポジショントークにはなってしまいますが、採用って新しいことをやればやるほどリソースがかかるので、全部を自分たちでやろうとせずにもっと外部の力に頼っていけばいいのに、と思います。
WHOMでは、プロのリクルーターのデータベースを持っていて、それぞれの企業の課題に応じて、適材適所・適時適量でそれを解決できる人材をアサインしています。
舟迫 最近、特にスタートアップ界隈ではどういった課題が多いですか?
早瀬 もともとはずっと「エンジニア採用」が課題だと言われていましたが、最近ではビジネス職も全然採用できなくなっていますね。エンジニア採用も引き続き苦労しているという前提ですが、PdM(プロダクトマネージャー)や事業開発といった、専門性の高いビジネス職が特に難しいようです。
舟迫 そういった状況の中で、これから日本のスタートアップ採用界隈はどう変わっていくのでしょうか?
早瀬 採用手法の多様化は、当然あると思います。先ほど言ったようなショート動画だったり、SNS経由だったり、リファラル、アルムナイなどなど…。手法の間口は広がっていきますね。
加えて、これは希望的観測を含めてですが、採用担当者の給料は上がっていくと思います。海外では顕著で、西海岸の採用マネージャーが1,600万円くらいもらっていたりします。もちろん為替の問題もあるので一概に比較はできませんが、そのくらい払って実力のある人を据えないと採用ができない、ということです。
舟迫 それは朗報ですが、逆に採用担当者の方も気が抜けないところもありますよね。どんどん新しい手法にキャッチアップしていかないと、価値を発揮しづらくなってくるといいますか。
早瀬 おっしゃる通りです。人事のキャリアとして、最初に採用から入って1〜2年経験を積んだら違う領域にいって、HRBPを目指して…という、採用担当を人事の「登竜門」的に捉えることが日本では一般的ですよね。
その気持ちはわかるのですが、個人的にはそうではなく、採用には4年5年というスパンできちんと向き合って取り組むべきだと思っています。
採用は成果がわかりやすいので、ちょっとやっただけで出来た気になってしまう。そうではなくて、もっと再現性を求めてスペシャリスト化していくことを期待しています。
今、日本は本当に過渡期にあるので、だからこそ差がつきやすい。採用は自社に閉じがちな世界なので、もっともっとオープンにいろんな情報を取り込んで試していってほしいです。
舟迫 やはり色々な方の知見を取り入れることも大事ですね。
早瀬 最近では「採用すごくうまくいってるんじゃないの?」という印象の企業からも「どうしたらいいですか」と頼りが入ったりしますよ。うまくいっている会社でも、もっともっとうまくいかせたい、と思って向き合っているんですよね。
それぞれの専門分野の知見があるので、ぜひ頼っていただければと思います。
舟迫 早瀬さん、本日はありがとうございました。
早瀬 ありがとうございました!(了)
【読者特典・無料ダウンロード】「秒で変わるAI時代」に勝つ。最新AIツール完全攻略ガイド
近年、AI関連サービスは爆発的なスピードで進化しています。毎日のように新しいツールがリリースされる一方で、SNS上では広告色の強い情報や、過大評価されたコメントも多く見受けられます。
情報量があまりにも多く、さらにノイズも混ざる中で、「自分にとって本当に使えるツール」にたどり着くことは、簡単ではありません。だからこそ、「正しい情報源を選び、効率的にキャッチアップすること」が、これまで以上に重要になっています。
そこで今回は、SELECK編集部が日々実践している「最新AIツール情報の探し方・選び方・使い方」のノウハウに加えて、編集部が推薦する、現場で使えるAIツール22選をすべてまとめてお届けします。